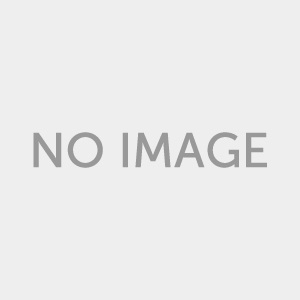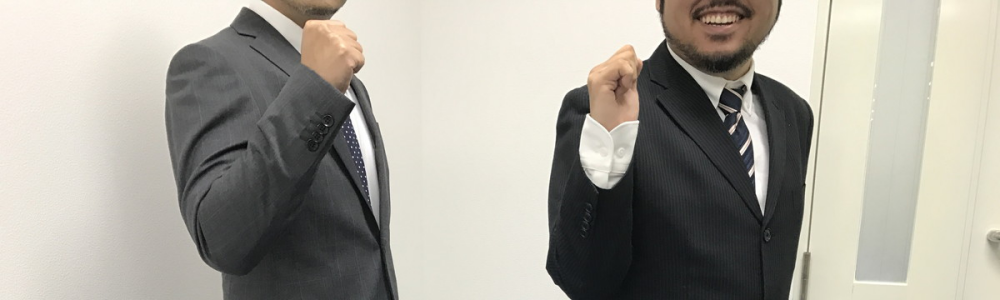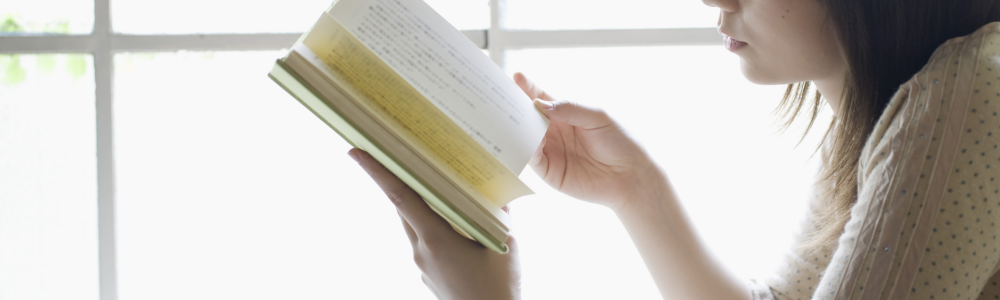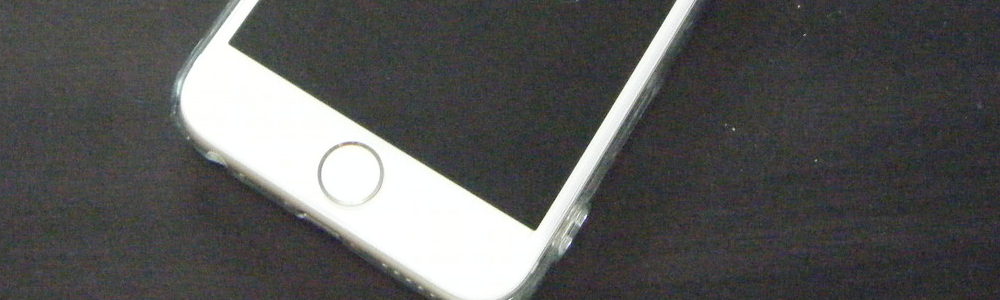建築士と建築家の違い
住宅やビルなど建物を作る時にはまず最初に設計図を作成し、それをもとにして実際の工事が開始されます。
このときの設計図を作成するための専門職が建築士です。
建築物を作る時には、その建物の規模や用途に応じて必要な設備を組み込んでいかなくてはいけませんが、そのためには高度な技術と知識が必要になります。
そのため設計を担当するためには事前に「建築士」の資格を取得しなくてはいけないように定められています。
「建築士」というのは国家資格の名称で、誰でも好きに名乗ることはできません。
一方で「建築家」というのはざっくりとした職業名称として用いられるときの言葉で、特に名乗るために資格や登録が必要なわけではありません。
とはいえ「建築家」を自称しているのに建築士の資格がないとなると設計を行うことができませんので、実質的には建築士としての資格があり、職業としての実績がある人が「建築家」を名乗るということが大半です。
「建築士」の定義ははっきりしていますが、「建築家」の定義は非常に曖昧です。
そこで一つの目安として社団法人日本建築家協会により、一定の要件を満たした会員のことを「建築家」と呼ぶように提唱されています。
その条件はいくつかありますが、代表的なものとしては協会に実績を申請して認められた者や、一級建築士として3年以上の実務経験がある者などが挙げられます。
一級建築士の特徴
建築士資格には「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の三種類があります。
そのうち最も難易度が高い資格は「一級建築士」です。
一級建築士は全ての建築物を設計することができるまさに設計のプロで、一般住宅だけでなく大規模なイベントホールや商業ビル施設、公共のモニュメントなどあらゆる建築物の設計をすることができます。
資格取得は医師や弁護士と並んで非常に難しく、大学・短大・専門学校において国土交通大臣の指定する養成課程を修了するとともに卒業後に一定期間の実務経験があって初めて受験資格を得ることができます。
二級建築士の特徴
二級建築士は一級建築士を取得する前にとることが多い資格です。
一級建築士になるためには卒業後の実務経験が必要なので、先に二級建築士資格を取得して働きそこから一級建築士試験を目指すというルートが一般的です。
担当をすることができるのは木造建造物や戸建住宅規模の小型の建造物に限定されます。
細かく担当できる建造物の床面積や構造などが定められているので、住宅建築専門の建築士資格と思ってください。
もう一つの木造建築士は二級建築士よりもさらに範囲の限定される資格で、名前の通り木造建造物のみを扱うことができます。
こちらは二級建築士の中でもさらに木造の限られた大きさまでの設計ができる資格ということになります。